JBL プロ用 15インチ スピーカー・ユニットの系譜
(独自研究:original research)
カタログ厨の妄想・・・
**厨って死語?
2020年5月:加筆
カタログ厨の耳学問を妄想という。JBLのユニットの基礎知識として系譜を追ってみた。ウチの箱が15インチ用なので15インチに絞る。
JBL型番はわかりにくい。特にプロフェッショナル向け15インチの22**は意味不明・・・記憶不能・・・
こちらのサイト「http://www.audioheritage.org」のカタログとフォーラムを参照した。
公開されているティール・スモール・パラメータ,実効質量(Mms),共振周波数(f0),最大変位(Xmax),等価容量(Vas),最大パワー,BLを参考にした。
トップ・プレート厚みとコイルの巻き幅もググって調べた結果から推測した。
1次情報の間違はよくあるので,あまり鵜呑みにしちゃいけません。本当は実物を確認できればいいのですが・・・
蛇足だが,日本ではスピーカー単体を「スピーカー・ユニット」,箱に入れると「スピーカー・システム」と呼ぶのが一般的。JBLは「トランデューサー」と呼ぶ。

JBL最初期のラインナップ(1948年のカタログより)
J.B.ランシング氏はアルテックから独立した後,自らが思い描く理想を実現するべく,D-101というスピーカーを発表した。 しかし,ボイスコイル直径は3"だし,フレーム形状もアルテックの515にそっくりだった。 挙句の果て,アルテックから商標に対してクレームが入る。
そんなこんなで全面的に再設計されて登場したのが「15"のD130」と「12"のD131」だ。 アルテックのスピーカーに比べて磁気回路やフレームのデザインが洗練されている。 そして駆動力を高める4"ボイスコルと浅めのカーブド・コーン,このふたつがキレの良い音の秘密だろう。
「D130」は音楽再生とPA(パブリック・アドレス)用に適しているとされ,のちにエクステンデッド・レンジ(フルレンジ)と呼ばれる。 同じカタログに「D130A」として低音用のスピーカーも紹介されている。D130Aはやがて"D"が省かれて「130A」と呼ばれる。
フルレンジ用のD130と低音用の130A,見かけ上の違いはD130はアルミ製の銀色のダスト・キャップだが130Aはコーン紙と同じ紙製だ。 D130は硬質アルミのダスト・キャップがスムースな高域再生を助けるとしているが,低音用の130Aには不要だ。
 JBL D130  JBL 150-4C |
それ以外にもボイスコイルの素材が異なる。D130はアルミニウム・リボンだが,130Aは銅リボンと記載されている。 軽量なアルミニウム・リボンはWE555ドライバにも使用されているハイエンド素材だが,アルミよりも銅の方が抵抗値が低く効率が良くなる。 もちろん総重量は銅の方が重くなるが,低音用スピーカーは重くもて支障がない,むしろ重い方が有利なので銅リボンを採用するのが当然の選択だと言える。
D130と130Aでは磁気回路も異なるらしい。 トップ・プレートの厚さがD130は0.28"(7.1mm)に対して130Aは0.35"(8.9mm)と言われている。 ボイスコイルの巻き幅もD130は0.29"(7.4mm)に対して130Aは0.31"(7.9mm)あるらしい。
しかし,手元に実物が無いので磁気回路の違いを確認することはできないのでカタログ値を追ってみる。
最初期のカタログではD130と130Aの重量は同じだ。年代を追うとカタログ表記の重量にブレがある。奥行き寸法も参考になるが,こちらも表記がブレる。 しかし,スタートアップ間もないランシング氏が何種類もの部品を使い分けたとは考えにくいので,最初期に限ってはD130と130Aは同じ磁気回路だったのではないだろうか。
なお,当初は130A:16Ω,130B:32Ωだったが60年代後半に130A:8Ω,130B:16Ωに切り替わっている。
少し時間が空いて1954年のカタログに「150-4」と「150-4C」が登場する。150-4が32Ω,150-4Cが16Ωとのことだ。 インピーダンスが高めなので複数台を並列駆動することが前提になっているようだ。
150-4は劇場向けの大型システムのために開発したユニットだ。 低音用ホーンを駆動するためにALTEC 515と同様の頂角の深いストレート・コーンを使っている。
D130のために新しく開発したカーブド・コーンを使わなかったことから,ランシング氏の技術本位のこだわりを感じる。 この奥行きの深いコーンは130系のフレームからはみ出てしまうので,フレームの外周部にリング状の部品を取り付け,かさ上げしてコーンを取り付けている。
150-4はパラゴンやハーツフィールドなどのホーンロードのかかるエンクロージャーに使われていた。 一方の130はC38などの箱型エンクロージャーで使われており,用途が区別されていたようだ。 150-4は1967年のカタログまで記載されている。
LE15の衝撃
 JBL LE15 |
ここでバート・ロカンシーという重要人物が登場する。
この人物はJBLからガウスを経由してパイオニアへ,そして「TAD」の技術顧問に就任する。 さらにレイ・オーディオの木下氏とも交流があるというから捨て置けない。その彼のルーツがJBLでの活躍だ。
それまで効率一辺倒だったJBLのスピーカー・ユニットに対して技術的・論理的なアプローチを導入して新たな方向性を示すことになる。
バート・ロカンシーが設計を主導したと言われているのが1960年に発表されたLEシリーズだ。 LEシリーズは当初「Low Efficiency」の略だとされていたがマーケティングの事情から「Linear Efficiency」の略とされることになった。 対照的にD130を筆頭とするDシリーズは「Maximum Efficiency」と称されるようになる。
LEシリーズは効率よりも低域側への帯域拡張と大振幅時のリニアリティを優先した設計になっている。 その方向性を端的に示しているのがLE15のトップ・プレートの厚みだ。
 D130とLE15の磁気回路の違い |
見るからに分厚いLE15のトップ・プレートは通常の2倍以上の厚さがあり,深い磁気ギャップを生み出す。 その中央に130Aと同様の短いボイスコイルを置くことで,コーンが大きく振れてもリニアリティが悪化しない構造を生み出している。 いわゆる「ロング・ギャップ,ショート・コイル」構造だ。
この深い磁気ギャップを十分に高い磁束密度で満たすため,断面積の大きなマグネットを背負っている。 同時にトップ・プレートとキャスト・ポット(鋳鉄製の壺型磁気回路,バック・ヨーク)の直径が拡大され,ポットの肩は丸みを帯びずに角張っている。 結果的にこの磁気回路は通常の1.5倍以上,実に9.1kgもの重量がある。
LE15のコーンはJBLの15"としては初めて厚みのあるコルゲーション入りコーンを採用しており,コーンの分割振動による高域のピーク発生を防ぎスムーズな音を実現している。 厚みのあるコーンは実効質量が60gから97gへと1.5倍ほど増し,ハイコンプライアンス・エッジ,つまり柔らかいロール・エッジとあいまってそれまで40Hzほどだったf0が一気に20Hzまで下がった。
白いロール・エッジは「ランサロイ」と名付けられたラバー・エッジだったが,70年代に黒いウレタン・エッジに変更され精悍な顔つきとなる。
同じ容積のエンクロージャーならば,f0が低く振動系が重い方が低域再生に有利に働く。このことによって実現される大振幅においてもリニアリティを保つ。 LE15は理論通りのアプローチをそのまま実践した技術的に馬鹿正直かつ贅沢なスピーカー・ユニットだ。
LE15は150-4の後継としてパラゴンにも搭載されることになる。ここはマニアの間でも是非がわかれるようだ。 個人的には中低音にホーンロードをかけていること,家庭用としてそれほど大音量を求めないことから,パラゴンにはマッチしていると思う。
なお,LE15は当初16Ωのみだったが,LE15Aは8or16Ωだったようだ。 LE15Bはしかし,インピーダンスとは関係なく,エッジをクロス・エッジとしたユニットだ。
LEシリーズのアプローチ
さて,LEシリーズにはLE14という異色のウーハーがある。 口径が14"ではあるが「重たいウーハー族」の始祖として挙げておいた。 「重たいウーハー族」はスタジオ・モニタ用として重低音を出すためのウーハーとして2230,2231,2235へと受け継がれていく。 同族には家庭用としては135A,136Aがある。
LEシリーズのラインナップから考えると,LEシリーズは家庭用の小型エンクロージャーから良質な低音を得ることを目的としていることに気づく。 ウーハーからツイーターまで多義にわたるLEシリーズは主に家庭用向けのラインナップであり,家庭用スピーカーの市場拡大に合わせてJBLが開発を進めていたことが分かる。
さてLE14の白いコーンはコーティング剤「アクアプラス」を塗ることによってLE15のコーンよりもさらに重さを増している。 振動系の重量増加は,より小型のシステムでも十分な低音を出すという設計意図を意味している。 ただし,能率は犠牲となる。アクアプラスを塗布した15"ウーハーは2230として後ほど登場する。
この時代,ラバーエッジの「ランサロイ」,白いコーティング剤の「アクア・プラス」といった素材名によるマーケティング手法が眩しい。
プロフェッショナルへの参入
 JBL D140F |
50年代から60年代初頭のJBLはパラゴンに代表されるハイエンドの美しい家庭用スピーカーを中心にビジネスを進めていた。 当時のプロ用スピーカー市場はアルテックが幅を利かせており参入が難しかった。 つまりスタジオでは604を入れた銀箱(612)が,劇場ではA7やA5に代表される武骨なスピーカーが多く使われていた。
JBLはスタジオ・モニタとしてLE15を搭載した「C50SM」というシステム・プランを1962年には用意していた。 C50といえばシステム型番「D50」のオリンパスが有名だが,同じユニット構成で型番末尾が「SM」のスタジオ・モニタが用意されていたことになる。
そんな1959年アルテックは604Dの後継機種として605Aを導入した。これが奇しくも転機となった。 605Aは磁石を小さくして磁気回路を弱めたため感度が低下しておりプロ市場では反感を買ってしまった。 1967年に604Eが登場するまでの8年間が空白となった。
JBLはキャピタル・レコードに気に入られたD50SMS7をベースに4320というスタジオ・モニタを開発。 605Aに対する反動もあり,標準原器ではあるがピーキーな604に対してフラットなパワー・レスポンスを持つ4320が徐々に認められてくる。 その後の70年代,JBLの43シリーズの躍進は日本のオーディオファンにとってもなじみ深いだろう。
このようなスタジオ・モニタの流れとは別の大きな潮流がプロフェッショナル市場への足掛かりとなる。
60年代初頭に出現したサーフ・ミュージックやロックン・ロールにJBLスピーカーを使うことが流行った。 とにかくデカい音が出したい目立ちたがり屋のギタリストが反応のよいJBLスピーカーに目を付けて自らスピーカーを交換するようになったというのだ。 フェンダーのアンプでは1959年にはファクトリー・オプションとしてJBLスピーカーを扱い始め,1962年にはレギュラー・ラインナップに顔を並べている。 特に「DualShowman」というモデルでは密閉型の大型エンクロージャーにD130を2発搭載しており巨大な出力トランスとの組み合わせで「メチャクチャデカい音」を出していた。
しかし,Dシリーズをそのままギターアンプに使うとすぐに飛んでしまう。 一説によればディック・デイルとレオ・フェンダーがJBLに乗り込んだと言われている。彼らはより高い耐久性を求めた。 そこでDシリーズの耐久性を強化するためにギャップ広げたり,サスペンションを強化するなど徐々に改良を施してFシリーズとしてまとめ上げた。 誰も予想しなかったことだが偶然にもこれがプロフェッショナル市場への躍進のきっかけになる。
当時の60年代初頭から中盤はポピュラー音楽の商業化が急速に拡大し,多くの聴衆に大音量を届けるステージ音響(PAやSRと呼ばれる)が急速に発達した。 初期のザ・ビートルズのコンサートではファンの叫び声しか聞こえないと言われていたが,ザ・フーなどのブリティッシュロックの台頭と共に大音量のエレキ・サウンドが普及してくる。
フェンダーとJBLの出会いは音楽が大規模に商業化していく激動の時代が実現させた奇跡のコラボレーションといえるかもしれない。 ハイパワーに強い4インチ・ボイスコイルを搭載したJBLスピーカーは壊れにくく,ギターアンプだけではなくステージ音響の中でも徐々に地位を築いていく。 そしてJBLとステージ音響を結ぶ最も強烈なキーワードは「デッドのWall of Sound」であり今現在でもこれを超えるシステムはないだろう。
 the Grateful Dead's Wall of Sound |
さてFシリーズは当初,15"のD130F,12"のD131Fがラインナップされた。 追ってエレクトリック・ベース用やオルガン用のD140F(15")や小口径のD110F(10")が追加された。
D130FはD130を改良し,耐久性を向上させたと言われているが一方,D140Fでは新たな試みを行っている。
D140Fは巻き幅が広いボイスコイルとD130の磁気回路を組み合わせている。 いわゆる「ショート・ギャップ,ロング・コイル」構造とすることによって大振幅によるリニアリティの低下を防ぎ,大出力時のパワー・コンプレッションを改善しようとしている。 大音量での音圧低下を防ぐことでパンチのある(英語ではキックとも言われる)中低音を実現した。
先に挙げたLE15は「ロング・ギャップ,ショート・コイル」によってリニアリティ確保を実現しようとしたが, リニアリティよりも大音量を安定して出力することを優先するために逆の構造を試したわけだ。
なお,コーンはLE15のコルゲーション入りコーンを流用し,LE15よりもコイルの巻き幅が広くなったことから振動系の実効質量が97gから105gに増加している。 さらに耐久性に優れたクロス・エッジを装備して,強力な低音再生に対応できるようにリファインされている。
D140Fのクロス・エッジには当初,1965年のオリンパスに採用されたPR15というドローン・コーンと同様のトリプル・ロール・エッジを使っていたが, より耐久性を高めるために1970年代前半に新素材を使ったダブル・ロール(M型)のクロス・エッジが新たに開発された。 それまでは振幅の小さい高効率スピーカーはフィックスド・エッジ,大振幅の低音用スピーカーはトリプル・ロール・エッジと区別されていたが, この新しいエッジは双方の改善版として統一的に置き換えられたようだ。
1971年のカタログより
 JBL 2220 |
ネットで参照できるJBLのプロフェッショナル向けカタログは1971年版が最古だ。 ここから15"トランデューサーだけを抜粋して分類してみる。
まずD130を祖とする「広帯域族」は2135がPA用フルレンジ,K130とK140が楽器用として挙げられている。
楽器用のFシリーズ時代はギャップ幅を広げたり,ボイスコイルやコーン,サスペンションを強化するなどマイナーチェンジが段階的に行われたようだが, Kシリーズは楽器用スピーカーとしての集大成とみることができる。
まず耐久性を高めるために高温に耐えるカプトン製ボビンを導入して耐入力が300Wに達している。 同時代のPA・SR用の2205は150W,家庭用の130Aは依然として90Wなので2倍・3倍の差だ。 シリーズ名のKは「Kapton」からとっているであろうことはまず間違いないだろう。 この冷戦の時代に当時の最先端素材を楽器用に使うという発想がいかにもアメリカらしい。
そしてプロフェッショナル・シリーズはキャスト・ポットの形状が家庭用モデルとは異なる。 2205や2220は台形型に絞られた奥行きの深いポットが使われている。 磁気回路が強化されていると言われており重量がやや増加しているが,マグネットを大きくしたわけではないようだ。 また,ギャップが広いと言われるがギャップはポール・ピースとトップ・プレートの寸法で決まるのでポット形状は関係ない。 したがってプロ用と家庭用にどのような違いがあるのか詳細は謎だ。
 家庭用とプロ用の違い:2231A vs 136A(L-300のカタログより) |
プロ用でもKシリーズは例外的に丸みを帯びたポットを使っている。 理由は分からないがギターアンプに搭載したときの顔を重視したか,もしくは形状的な下位互換を持たせたのかもしれない。 とはいえSFG時代には家庭用とプロ用の形状が統合されることも合わせて考えると,台形と丸型の使い分けはデザイン面での差異化を意図したのではないかと思われる。
 磁気回路の違い:2215 / 2205 / K130 |
さてここまでは前置き。ここからが本題だ。 低音用15"トランデューサーに焦点を絞ろう。 2205,2215,2220の3種だ。22**これをひも解いていく。
まず,2205と2220はPA・SR(Public Address・Sound Reinforcement)用だが,LE15のプロ用である2215はスタジオ・モニタ用途だろう。
PA・SR用途では4560や4530のようにホーンロードをかけたエンクロージャーが用意されていた。 当時はキャビネットやエンクロージャーの図面が公開されており,ユニットのみを購入してオリジナル・システムを構築することもよく行われていた。

|

|
|
JBL 4560+2220 フロントロード式ホーン・エンクロージャー |
JBL 4530+2205 リアローディング式ホーン・エンクロージャー |
2205と2220の二つを大別すると,2205は耐久性に優れたハイパワーモデル,2220は中低域を重視した高能率モデルだ。
まず2205はFシリーズの低音用ユニットD140FをPA・SR向けにアレンジしたユニットといえる。 センターキャップはアルミではなくペーパーだが,コーンはD140Fと同様にLE15のコルゲーション入りコーンを流用した。 磁気回路とコイルはK140と同じロング・コイル,ショート・ギャップだ。
この2205はリアローディング(バックロードホーン)のエンクロージャである4530や4520に搭載して最低域を増強して近距離用とされている。 つまりライブ・ハウスやディスコなどの高音圧の低音を必要とする用途向けだ。
一方で2220は130Aの直接的な子孫といえるが,大きな振幅に対応できるようにトップ・プレートが厚く,磁気回路の重量が重くなっている。 ボイスコイルの巻き幅を実測してみるとDシリーズよりも幅が広く抵抗値も少し高い。 コーンも21057というD130系よりも丈夫で少し重たいコーンを搭載してより高い音圧を出せるように改良したようだ。 実効質量はD130系の60gに対して70gとなっている。
この2220はもっぱらフロントロードのエンクロージャである4560や4550に入れて使われ,中低音の指向性を絞り,能率を稼ぐことで最大音圧を高めている。 長距離大空間用,つまりコンサートや劇場向けとされている。
2215はスタジオ向けと分類してみたが構造的にはLE15そのものでポットの形状も同一だ。 LE15の耐入力は当初は60Wしかなかったが,途中120Wになり2215Hでは150Wまで強化されている。 家庭用より大音量を求められるスタジオ・モニタ用なので,耐熱性を改良したボイスコイルに変更されていったのだろう。
ちょっと横道にそれるが,KシリーズにはK145という異色のユニットもある。 150-4の後継と言われているが,頂角の深いコーンを持ち,150-4と設計コンセプトは似ているが磁気回路はLE15から流用しており似て非なるユニットだ。 とはいえ,K145の後継ユニットE145は150-4Hと名付けられて家庭用の大型システム「エベレストDD5500」に採用されているのでやはり方向性は似ているのだろう。
なお,プロ用は末尾文字が"A"が8Ω,"B"が16Ω,"C"が32Ωとなっている。
2216と2230が登場
1974年のカタログには新たに2216と2230が登場して15"低音用ユニットのラインナップをにぎやかにしている。
2216は2215をクロス・エッジにしたもの。4320というスタジオ・モニタが好評でそれをさらに改良した4325というモデルに搭載されたとのことだ。 磁気回路はそのままにエッジの耐久性を改善し,ついでにコンプライアンスを下げてキレを良くしたのだろう。2216の家庭用モデルはLE15Bと呼ばれる。
そして突如登場した「JBLの白いウーハー,2230」はスタジオ・モニタの低音域の再生限界を下げるために,LE14と同様にコーン紙に白いコーティング「アクアプラス」を施して重量を増している。
なお「マグネット・コーティング」ではない(この単語に反応すると歳がばれる)。
LE14と2230を祖先とする実効質量が150g前後の「重たいウーハー族」は今後スタジオ・モニタ用として系譜を刻むことになる。
1976年のカタログに登場する2231はスタジオ・モニタ用のウーハーとして汎用的な立ち位置になる。型番から考えても2230の後継機種だろう。 白いコーティングはやめて,代わりにマス・コントロール・リングというアンチモンの重りをボイスコイルに取り付けて実効質量を増している。
2231は磁気回路の設計としては2205と同様に効率の良いロング・ボイスコイル,ショート・ギャップを採用しているが,コイルの巻き幅は16mmに拡大されている。 しかし,振動系・サスペンション系は2215と同様のハイコンプライアンス設計なので2215よりも重さを増した振動系と相まってかなりフラフラなユニットに仕上がっている。 大振幅駆動時にボイスコイルがギャップから飛び出しやすくなるため,おそらく大音量には弱かったと思われる。
磁気回路の違い
ここでJBLのプロフェッショナル用15"トランデューサーのアルニコ時代に限り磁気回路の違いについてまとめてみた。 JBLの広報資料にD140FとLE15の断面写真が掲載されていたのでそれを参考にした。2220は実物も参照した。
最初に設計されたD130を基本として比較していく。
まず,LE15は大口径マグネットを採用し,トップ・プレートとバック・ヨークの肉厚が際立っている。 ボイスコイルの巻き幅はD130と同一だがトップ・プレート位置がコーンから遠くなると共にギャップが深いのでボビンは高くなる。
2220はポット形状が台形になり重量が増している。 磁気回路が強化されていると言われているが,D130よりも大きなマグネットを取り付けることはできないので,もし磁力を強化するなら磁石の素材を変えるしかなかっただろう。 なお,2220のトップ・プレートは2231と比較するとやや厚い。
2231はボイスコイルの巻き幅が16mmと広くなりいわゆるロング・コイルとなる。 トップ・プレートの厚さはD130と同じだがコイルの巻き幅が広いためボビンが高くなり空気抜きの穴がなくなる。
 D130 |
 LE15(Short coil/deep gap) |
 2220 |
 2231(Long coil/short gap) |
1980年のカタログより,SFGの登場,アルニコ磁石からフェライト磁石への転換
アルニコ磁石はアルミニウム,ニッケル,コバルトの合金であり最大磁束密度が高く,効率が良い。 アルニコは高級,フェライトは安価というイメージがあるが素材としの価値が高いので仕方ない。
1978年,それまでアルニコ一辺倒だったJBLがフェライト磁石へ舵を切った。 この転換には所説あるようだが,あのような巨大なアルニコ磁石を使い続けるのは浪費以外の何物でもない。 技術革新も含めて時代の流れと考えるのが妥当だろう。
 |
アルニコとフェライトの違いの大前提として物性が全く異なるため,磁気回路の形状が大きく変わる。 アルニコ磁石は飽和磁束密度が高く保磁力が弱いため断面積が小さく縦長のマグネット形状が適する。 一方,フェライト磁石は飽和密度が低く保磁力が強いため断面積が大きく薄いマグネットが適する。 この違いから一般的にアルニコ磁石は磁気回路の中心部に磁石を配置する内磁型となり, フェライト磁石は磁気回路の外側に磁石を配置する外磁型となる。
フェライト磁石を使ったJBLの「SFG」と呼ばれる磁気回路は当時最先端の研究成果が盛り込まれたいかにもJBLらしい贅沢で欲張りな設計だ。 まず「シンメトリカル・フィールド」つまり磁界の対称性を高めて2次歪みを減らすためセンター・ポール・ピースにアンダーカットを施している。 そしてコイルによる起電力をショートして磁気変調を減らすためにポールピースの根元に抵抗値が極小となる巨大なショート・リングも取り付けている。 このようにアルニコ磁石からフェライト磁石へグレードダウン・イメージとならないように多くのブレークスルーが必要だったのかもしれない。 実際に2次歪み3次歪みはアルニコ・モデルよりも低減された。
また,SFGは旧来のアルニコ・モデルに対してコーン・アッセンブリの互換性を維持できるように設計されている。 トップ・プレートはマグネット面積の拡大に伴い大口径されているが,ポール・ピース面とコーンやコイルの寸法関係が変化しないようにその分バスケットの肉を削り込んでいる。 そのためフレームの一部までが削られてしまっているが,こんなところにコーン・アセンブリを共通化させるための苦慮が表れている。
とはいえ互換性を維持できなかったモデルもある。 大型マグネットを搭載するためにやや強引に流用設計したLE15/2215/K145はトップ・プレートとコーンの距離が遠かったため,フェライト・モデルのLE15H/2215H/E145と下位互換性を保つことができなかった。 トップ・プレートの厚みをそろえることはできたが,しかし長大なギャップを高い磁束密度で満たすことはできず磁束密度の低下した分アルニコ・モデルよりも感度が低下してしまっている。
SFGの低音用15"ユニットのラインナップを確認してみよう。 1971年のラインナップ(2205,2215,2220)に重いウーハー族の2231を加えて2205H,2215H,2220H,2231Hの4種類でスタートしている。 この4種類はそれぞれの用途に合わせた独自の個性をもつためラインナップに隙が無い。
なお,それまで150Wだった耐入力はSFG時代に至ってようやくKシリーズと同等の300Wに達した。 SFG化と同時にカプトン・ボイスコイルに切り替えられたとみるべきだろう。
楽器用のKシリーズはEシリーズへと置き換わり,2135はE130に集約される。 Eシリーズは他のモデルよりも厚いフェライト・マグネットを採用することによりKシリーズと比較しても磁束密度が上がり感度もさらに向上している。
なお,SFG時代は末尾文字が"G"で4Ω,"H"で8Ω,"J"で16Ωだ。
プロ用ではないので余談だが,D130HやLE15H,150-4Hというモデルもある。
2225と2235の登場(1982年)
フェライト磁石のSFG導入当初,15"ユニットは4種だったが,1982年のカタログで3種に集約される。
新登場の2225はハイパワー族の2205の耐入力をさらに向上させ,最大音圧を稼ぐための子孫だ。 2231で実績を積んだ巻き幅16mmのボイスコイルを流用して,リニアリティ維持しつつ最大音圧を稼ぎ,サスペンションをガチガチに固めて耐久性を向上したユニットだ。
新登場の2235は2231直系の重いウーハー族の子孫で,コイルの巻き幅16mmから19mmに増やすと共に,サスペンション系を改善して大振幅に対応しているようだ。 コンプライアンスを2215や2231よりも低く設定することで大音量再生時の破綻を防いでいる。スタジオ・モニタの4430などに使われてる。
なおこの2235には2234という亜種があるが,2234は4435というダブルウーハーのスタジオ・モニタ用で,マス・コントロール・リングが取り付けられておらず実行質量が軽い。 当初4435では2235と2234をスタガー的に使うことを考えていたようだが,最終的に2234のダブルに落ち着いたようだ。 なお,4435はダブルウーハーではあるが内部には仕切りがあるそうだがこれも余談。
LE15を祖とする贅沢族の2215は自然消滅の道を歩む。ググってみたが2215Hは用途に乏しかったようだ。 UREIのお化けスタジオ・モニタ,813C,815Cに搭載されていることが確認できたがそれ以外ははっきりしない。
LE15を祖とする贅沢族の系譜は2215の消滅でいったん途切れたが,1500ALが贅沢族と重たいウーハー族の血統を継いでいる。 1500ALは長大な磁気ギャップに重たい振動板の組み合わせ,つまりLE15と2235を組み合わせたと考えればよい。つまり,スタジオ・モニタ直系。 重苦しくて鳴らしにくいという声もあり評価は分かれるようだが・・・
参考までに18"ユニットはこの年まではK151/E155だけだったが,2240と2245という18"ウーハーが登場している。 これらは完全にサブウーハー用。SFGからVGCへの布石であり,高音圧の低音は18"に任せるという流れを感じる。
ハイパワー進化系2226の登場と2220の引退(1990年)
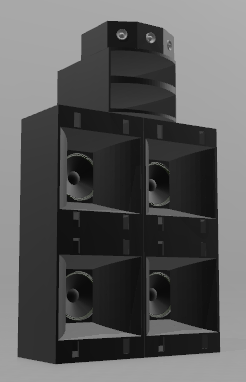 JBL 4560 + 2350 + 075 |
130A直系の高能率ウーハーである2220A/B/C/H/Jはホーンロードをかけて中低域で高音圧を得るという用途で長らく使われてきた。 2220を搭載した複数の4560エンクロージャーと2350などの高域用ホーンをスタックして積み重ねることで会場の規模に応じて必要な音圧を確保することができた。
ところが,時代はホーンロードからダイレクト放射へと流れていく。要因は三つあると考えている。
まずひとつはサブウーハーの普及だ。コンサート用SRでは迫力ある低音を求めてサブウーハーの導入が進められていく。 4560などのフロントロード・ホーンは200Hz以上の中低域に効果的だが100Hz程度の低域ではホーンの増強効果が得られず恩恵にあずかれない。 必然的に4530などのバックロード・ホーンを追加することになるが40Hzの最低域まで考えると空振りしてくる。 低音で大音量を出すためには動かす空気の量,つまり面積と変位を大きくすることが必要なため18"以上の大口径のサブウーハーが普及してくる。 チャンネル・ディバイダーで帯域分割して低域をサブウーハーに任せると,余計な低域がカットされるので中低域を担当するユニットは楽になる。 大振幅の低音はコーンの変位が大きく,ユニットを破壊する原因となるだけでなく,前兆として「音が割れる」ので大音量再生を目的とするなら有害でしかない。 破壊的な大振幅の低音をサブウーハーに任せてしまえば,中低音を担当するユニットによりパワーを入れることができ,その分音圧を稼ぐことができる。
強力なサブウーハーが普及すると中低域は楽になるため4560のような低音用ホーンは不要になり,2220+4560という黄金コンビは自然と廃れていく。
ふたつめの要因はシネマ用途においてホーンロードによる色付けとEQ補正による音質劣化がクローズアップされ始めたことだ。 素直な周波数特性のダイレクト放射,つまりバスレフ型が見直されることになる。
 JBL SR4733A + SR4719A |
三つめは同時に数多くのスピーカーをスタックした場合に発生する音波の干渉だ。 これが問題視され,EQでは補正できない指向性の暴れに対処する必要性が認識されてきた。 干渉を起こさないためにはスピーカーの数を減らしてできるだけ密集配置すればよい。 密集配置するために横幅の狭いトラぺゾイド型(台形)エンクロージャーが選ばれるようになってくる。
小型のダイレクト放射エンクロージャーに入れて高い音圧を実現するためにウーハーに大電力を叩きこむ。 パワーアンプがソリッドステート化して1000Wを超えるパワーを出せるようになったことも要因の一つだ。
1990年,こうしたニーズを満たすSR4700シリーズというSR用システムに搭載されるべく2226が登場した。高出力で高音圧が得られるユニットとして登場したのだろう。 直接的には2225を改良して600Wの耐入力を実現するべく優れた冷却機構を持つVGC磁気回路を開発し, これに大振幅に耐える巻き幅19mmのボイスコイルとロングストローク・サスペンションを組み合わせたと考えるの筋だ。 サスペンションは2225よりは柔らかいがスタジオ用の2235に比べるとガチガチに固い。
f0は40Hz,実行質量は98gで,2225とほぼ同等だ。 特徴的なのはE130以外では久しぶりにボイスコイルをアルミリボンにしたことだ。 おそらくコイルの巻き幅が増えた分,コイルが重くなり効率が低下することを嫌ったと思われる。
2226はその後長年にわたり(今でも現役)JBLの代表的な15"ユニットとして活躍している。
そして悲しいことにランシング氏の遺産である130系の直系子孫として50年近くJBLサウンドを支えてきた2220は1990年のカタログには記載されていない。
ランシング氏がデザインした優雅で美しい曲線のフレーム,シンプルで華奢に見えるが実は強度を得る工夫も十分に施された考え抜かれたフレーム。 2226はこのフレームを使った最後のユニットとなってしまった。
70年間もの長きに渡って輝きを失わない一連の15"ユニット群からはランシング氏の熱い魂を感じる。
1998年のカタログより
TRシリーズ,MRシリーズや,EONシリーズなど見知ったラインナップになっているが,やはりSR4700シリーズが直系子孫として異彩を放っている。
15"では2227という2220系の子孫を思わせるユニットがSRシステム専用として登場するが短命に終わったようだ。 2227はSVGという磁気回路を持つが,バスケットは形状は18"ウーハーに似ている。
そして大規模コンサート向けのSRシステムはラインアレイの時代となるが,それはもう現代。レガシーな話題ではない。
ラインアレイ・システムは多数のスピーカーを垂直方向へ一直線に並べて線状音源を作り出すことによりスタックによる干渉の問題を解消した。 しかし線状音源を作り出すため形状が制限されるので低音には8"〜12"を使用することが多い。 大型のラインアレイたとえばJBLのVERTECシリーズは15"を使用しているが今後も軽薄短小のトレンドは止まらないだろう。
15インチ(三八と言う人もいる)は大型恐竜のように絶滅の道を歩むのか。 最新のサウンドバーに使われる5センチ程度のスピーカーと4インチ(10センチ)ボイスコイルを見比べると滅びゆく大艦巨砲主義を感じさせられる。 ロマンとしか言いようがない。いや,それはただの妄想だろう。
15"系譜まとめ:D130直系(広帯域族:Extend Range)

|
f0=40Hz,mms=60gの広帯域ウーハー |
15"系譜まとめ:130A系(高能率族:High Efficiency)

|
f0=37Hz,mms=70gの中低域ウーハー |
15"系譜まとめ:LE15系(贅沢族:Deep Gap, Heavy Magnet)

|
f0=20Hz,mms=97gのウーハー |
15"系譜まとめ:2235系(重たいウーハー族:Studio Monitor)

|
f0=20Hz以下,mms=150g以上のウーハー |
15"系譜まとめ:2226系(ハイパワー族:High Power)

|
f0=40Hz程度,mms=100g前後のウーハー |

殺風景なので「3D Builder」で絵をかいてみた。スピーカーをモデリングするのは楽しい・・・でも音は出ない・・・
Copyright(C) Since 1999 Y.Hosoya. All rights reserved.